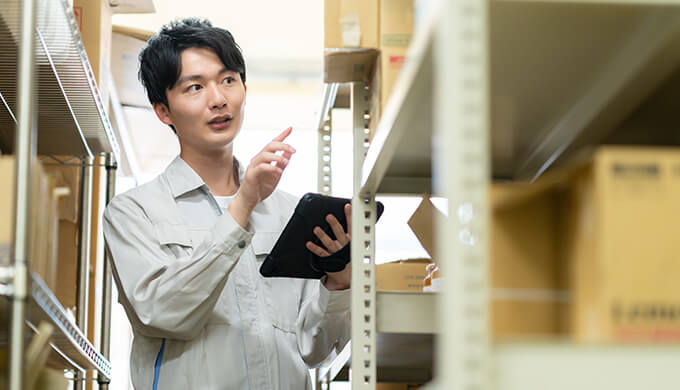物流業務におけるロケーション管理とは?在庫精度を高める方法も解説

物流や倉庫業務を効率化するうえで欠かせないのが、「ロケーション管理」です。
ロケーションとは、倉庫内の商品がどこに保管されているかを明確にするための“住所”のような仕組みのことで、適切に管理することで在庫の把握が容易になり、ピッキングや補充などの作業スピードが向上します。
この記事では、ロケーション管理の基本的な考え方から、導入のメリット、運用方法、効率化のポイントまでを解説します。
物流におけるロケーションとは?
ロケーションとは、倉庫内で商品を保管・管理する際の「位置情報」や「住所」を表す仕組みのことです。一般的には、ゾーン(エリア)→棚→段→区画といった階層構造でロケーションコードを設定します。
たとえば「A-03-B2」というコードであれば、Aゾーンの3列目・B棚・2段目という意味になります。これにより、倉庫内のどこに何の商品があるかを正確に把握できます。
ロケーション管理は、ピッキング効率の向上、誤出荷防止、在庫精度の向上に直結するため、物流や倉庫業務では欠かせない工程となっています。
ロケーション管理の重要性
ロケーション管理の最大の目的は「在庫精度の向上」です。どの商品がどの位置にあるのかをリアルタイムで把握できるため、在庫の過不足や誤出荷を防ぎます。
また、ロケーションコードに基づいて作業動線を最適化できるため、ピッキングや入出庫の時間短縮も期待できます。
さらに、明確な配置ルールによりヒューマンエラーを減らし、経験の浅いスタッフでも正確に作業を進められる環境を整えられます。限られた倉庫スペースの中で、ロケーション単位での配置を最適化すればデッドスペースが減り、保管効率も高まります。
結果として、倉庫全体の見える化が実現し、経営判断や在庫補充計画がデータに基づいて行なえるようになります。
ロケーション管理は単なる位置の把握ではなく、「現場の生産性と品質」を支える基盤なのです。
ロケーションの種類と構成要素
ロケーションには
- 固定ロケーション
- フリーロケーション
の2種類があります。
固定ロケーションは、特定の商品を常に同じ場所に保管する方法で、管理がシンプルでわかりやすくなりますが、スペース効率が下がることがあります。一方で、フリーロケーションは、入荷状況に応じて空きスペースに柔軟に配置できる方式で、保管効率を最大化できます。
また、ロケーション構造は
- ゾーン
- エリア
- 棚番
- 段
- 区画
といった階層構造が基本です。たとえば「A-01-2-B」のようにコード化し、WMS(倉庫管理システム)と連携することで検索・照合が容易になります。
また、SKU(在庫管理単位)ごとにロケーションを割り当てることで、似た商品同士の混在を防ぐことができます。結果、ピッキングミスの削減につながります。
ロケーション管理を導入するメリット
ロケーション管理には次のようなメリットがあります。
ピッキングスピードを向上できる
ロケーション管理を行なうことで、商品の位置が明確になり、スタッフが迷うことなくピッキングできます。動線を最短化できるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。結果として、出荷リードタイムを短縮し、顧客満足度の向上にもつながります。
誤出荷・誤梱包の削減を期待できる
ロケーションコードに基づいた作業指示が出せるため、似た商品やバリエーション違いの誤出荷を防止します。特にアパレルや雑貨などSKUが多い業態では、バーコードスキャンと併用することでヒューマンエラーをほぼゼロにできます。
入庫~出庫までのリードタイムを短縮できる
ロケーションを適切に設定すれば、入庫から保管、ピッキング、出荷までの流れがスムーズになります。入庫時の配置ルールを統一することで、次工程への引き継ぎがスピーディーになり、出荷リードタイム全体を短縮できます。
新人教育を効率化できる(属人化防止)
倉庫内のロケーションが明確になっていると、誰でも同じ作業ができる仕組みとなります。新人スタッフでも短期間で業務を習得できるため、ベテラン依存の属人化を防げます。マニュアル化しやすく、教育コストの削減にもつながります。
在庫情報を一元化できる
ロケーション単位で在庫を管理することで、数量、場所、ロット、状態が一目で把握できます。システム上でリアルタイムに更新されるため、複数倉庫や拠点間での在庫情報共有もスムーズです。これにより、販売機会損失や二重発注を防げます。
ロケーション管理の導入方法
ロケーションコードをルール化する
ロケーション管理を正確に機能させるには、まず「ロケーションコード」を体系的にルール化することが大切です。倉庫をゾーン・棚・段・区画といった階層構造で分け、それぞれに一貫した命名ルールを設定します。
たとえば、「A-03-2-B」であれば、Aゾーン・3番棚・2段目・B区画といった具合です。誰が見ても一目で場所を特定できるようにすることで、ピッキングや補充のスピードと精度が格段に向上します。
また、システムと連携してコードを自動生成・登録できるようにすると、ヒューマンエラーの削減にもつながります。運用開始前に、全スタッフが理解できるルールブックを作成し、共通認識を徹底することがポイントです。
入庫時の登録(バーコードやスキャン連携)を正確に行なう
入庫時には、商品がどのロケーションに配置されたかを正確に登録することが重要です。バーコードスキャナやハンディターミナルを活用し、商品情報とロケーションコードを即時に紐づけましょう。これにより、手入力による誤登録を防ぎ、リアルタイムで在庫情報を更新できます。
また、商品ラベルにロケーションコードを印字しておくと、再配置や棚卸時の照合もスムーズになります。特に、多品種・多ロットを扱う倉庫では、この入庫プロセスの精度が在庫精度全体に直結します。
登録手順を標準化し、スキャン忘れを防ぐチェックリスト運用を組み合わせることで、現場の安定稼働を実現できます。
ピッキング時に商品コードとロケーションコードを照合する
出荷作業においては、ロケーションコードをもとにピッキングリストを自動生成し、バーコード照合によって正しい商品を取り出すことが基本です。ピッキング時に商品コードとロケーションコードをスキャンすることで、誤出荷を防止できます。
また、WMSやスマホアプリと連携することで、作業者の端末に最適なピッキング順序や動線が自動表示され、効率的な作業が可能になります。ダブルチェック体制を導入すれば、検品精度もさらに向上します。
照合プロセスをルール化することは、作業の属人化防止と品質安定化の両面で大きな効果を発揮します。
棚卸・補充作業を最適化する
ロケーション単位で在庫を把握できるようになると、棚卸作業が大幅に効率化されます。従来のように全倉庫を一括で確認する必要がなく、特定ゾーンごとの部分棚卸が可能になります。また、システムと連携すれば、在庫差異の自動検知や棚卸履歴の蓄積も容易です。
さらに、補充作業においてもロケーション管理は有効で、補充すべき棚をシステムが自動的に提示することで、作業の抜け漏れを防げます。適正在庫数の維持と、入出庫作業のスムーズな連携を実現するうえで、ロケーション管理は現場の生産性向上に直結します。
効率的な倉庫内動線を設計する
ロケーション管理の効果を最大化するには、倉庫レイアウトと動線設計が欠かせません。
出荷頻度の高い商品は出入口付近や主要通路沿いに配置し、低頻度品は奥のエリアにまとめるなど、ピッキング効率を意識したゾーニングを行ないましょう。商品特性や季節変動に応じてゾーンを再構成することも重要です。
また、作業動線を分析して最短経路を設計すれば、1件あたりのピッキング時間を短縮できます。ゾーンごとに担当者を配置し、在庫の偏りや混在を防ぐ体制を整えることで、作業効率と品質の両立を実現できます。
ロケーション管理を効率化するシステム
ロケーション管理では、効率化を実現できるシステムもあります。
WMS(倉庫管理システム)によるロケーション管理を導入する
WMSを導入すれば、ロケーション単位で在庫状況をリアルタイムに把握できます。入庫・出庫・棚卸などの作業データを自動で記録し、ヒューマンエラーを防止。また、作業指示やピッキングリストも自動生成されるため、現場の生産性と在庫精度が飛躍的に向上します。
ハンディターミナルやスマホアプリを活用する
ハンディターミナルやスマホアプリを利用すると、入庫・出庫・補充などの作業をその場で記録でき、リアルタイムな更新が可能になります。バーコードスキャンと組み合わせれば、誤登録を防ぎつつ効率的な現場運用を実現できます。
バーコード・QRコード・RFIDなど識別技術を導入する
識別技術を導入することで、在庫の識別精度とスピードが大幅に向上します。特に、RFIDは非接触で一括スキャンができるため、棚卸時間を短縮し、在庫差異を最小化できます。規模やコストに応じて適切な技術を選定することが重要です。
在庫マップツールを利用する
在庫マップツールを活用すれば、倉庫全体を可視化し、どこに何が保管されているかを一目で把握できます。作業者は画面上でロケーションを確認しながらピッキングできるため、教育時間を短縮できたり、誤出荷を防止できたりします。
ロケーション管理を導入する際の注意点
過剰なルール設計では運用負荷が大きくなる
ロケーション管理は精密であれば良いというものではありません。あまりに細かくルールを設けすぎると、現場での運用負荷が増し、かえって作業効率を下げてしまうリスクがあります。
たとえば「区画単位でのコード過多」や「商品ごとに細かすぎる配置制限」などは、現場が混乱する原因になります。
理想は“管理しやすく、理解しやすい”ルール設計です。現場スタッフが直感的に動ける程度のシンプルさを保ちながら、必要な精度だけを担保することが重要です。
最初から完璧を目指すのではなく、導入後に改善を重ねながらルールを洗練させるほうが、現場への定着と成果につながります。
棚番やコードの重複が起こると混乱する
ロケーションコードが重複していると、どの棚にどの商品があるのか判別できなくなり、誤出荷や在庫ズレの原因になります。特に複数倉庫やエリアをまたぐ運用では、コード体系を標準化していないと重複リスクが高まります。
導入前に「ゾーン→棚→段→区画」といった一貫性ある構造を定義し、コード生成ルールを全社的に統一することが大切です。また、システム上で重複チェック機能を活用し、登録時に警告が出る仕組みを作ると安心です。
倉庫レイアウト変更時や増設時にも、コード整合性を再確認し、常に一意性を保つことで混乱を未然に防げます。
データ入力をミスすると在庫ズレが起きる
ロケーション管理では、正しいデータ登録が運用の根幹です。入庫時や出庫時に商品コードやロケーションを誤って入力すると、在庫数量や位置情報が実際と異なり、在庫ズレが発生します。
これが続くと、棚卸や出荷計画に影響し、顧客への納期遅延や誤出荷につながる恐れもあります。入力作業はなるべく自動化し、バーコードスキャンやWMS連携を活用することで、ヒューマンエラーを最小限に抑えましょう。
また、ダブルチェック体制を設けて登録内容を確認する運用ルールを整備することも効果的です。データの正確性が、ロケーション管理全体の信頼性を左右します。
現場スタッフと運用ルールの不一致が起きることがある
システム上の設計と現場の実際の作業が一致していないと、ロケーション管理はうまく機能しません。
管理部門が作成したルールが、現場の動線や作業習慣と噛み合っていないケースは少なくありません。こうした乖離を防ぐためには、導入段階から現場スタッフを巻き込み、意見を反映した運用設計を行なうことが重要です。
また、ルール変更や倉庫レイアウトの更新時には、関係者全員に周知し、教育やトレーニングを実施することが欠かせません。システム上の理想と現場実態のバランスをとることで、無理のない定着と運用精度の向上が実現します。
定期的なメンテナンス・改善を行なう必要がある
ロケーション管理は、一度導入して終わりではありません。商品の入れ替えやSKUの増加、倉庫レイアウトの変更など、運用環境は常に変化します。そのため、定期的な棚卸や運用見直しを行ない、ロケーションコードや配置ルールを最新の状態に保つことが大切です。
定期的な点検により、データの整合性やシステム連携の不具合を早期に発見できます。また、現場スタッフからのフィードバックを反映し、より実務に即した改善を行なうことも効果的です。継続的なメンテナンスが、在庫精度と作業効率を長期的に維持するカギとなります。
ロケーション管理を改善するステップ
では、具体的にどのようにロケーション管理を改善していけばいいのか見ていきましょう。
現状分析(倉庫レイアウト・SKU特性の把握)
改善の第一歩は、現状の課題を明確にすることです。倉庫内の動線や保管スペースの使われ方、SKU(在庫管理単位)の特性を詳細に把握しましょう。
出荷頻度や商品のサイズ・形状などを分析することで、ロケーション配置の最適化ポイントが見えてきます。
現場スタッフへのヒアリングやデータ抽出を通じて、非効率なゾーンやムダな動線を特定することが、改善計画の基盤になります。
ロケーション設計(ゾーン分け・コード体系の構築)
現状分析の結果をもとに、倉庫をゾーンごとに分類し、最適なロケーション構造を設計します。たとえば「高頻度出荷ゾーン」「長期保管ゾーン」「返品対応ゾーン」など、用途別にエリアを明確化します。
次に、棚・段・区画を体系化したコードルールを設計し、誰が見ても分かる一貫性のある命名にします。ゾーン分けとコード体系を整備することで、在庫の可視化と作業効率の両立が可能になります。
試験運用とスタッフ教育
設計したロケーションルールは、いきなり全体に適用せず、まずは限定的な範囲で試験運用を行なうのが効果的です。実際の作業フローの中で問題点や改善点を洗い出し、運用マニュアルをブラッシュアップします。
同時に、スタッフへの教育・トレーニングも重要です。現場が新しいルールを正しく理解し、スムーズに実践できるようサポートすることで、導入の定着率が高まります。
システム連携・自動化の検討
ロケーション管理の精度と効率を高めるためには、WMS(倉庫管理システム)やバーコードスキャンなどとのシステム連携が欠かせません。
手作業中心ではヒューマンエラーが発生しやすく、データ反映にも時間がかかります。
自動化によって、在庫更新・照合・棚卸をリアルタイムで行なえる環境を整えることで、業務全体のスピードと正確性を大幅に向上できます。
定期的な棚卸とPDCA運用
ロケーション管理は、導入して終わりではなく継続的な改善が必要です。定期的に棚卸を実施し、実際の在庫とシステム上のデータを照合して精度を確認します。
差異が見つかった場合は原因を分析し、改善策を講じて次の運用に反映させます。
このPDCAサイクルを継続的に回すことで、常に最新かつ最適なロケーション管理体制を維持できます。
まとめ
ロケーション管理の改善は、倉庫全体の効率化と在庫精度向上に直結します。
現状を正しく分析し、明確なルール設計とシステム連携を行なうことで、ミスの少ないスマートな物流運用が可能になります。
定期的な見直しと改善を続け、安定した物流サービスを実現しましょう。